京大学生新聞編集員のブログです。
編集員の身の回りの話や、編集現場の裏話などを(自重しつつ)書き込んでいきます。(20080908開設)
プロフィール
HN:
京大学生新聞
年齢:
52
性別:
非公開
誕生日:
1973/04/01
職業:
学生記者
趣味:
レイアウト、記事作成、カメラ、広告取り……etc
自己紹介:
1973年(昭和48年)に産声を上げた、京都大学の学生新聞です。
カテゴリー
ブログ内検索
最新コメント
[01/18 Michalguavy]
[06/26 妙]
[06/26 菜]
[06/09 妙]
[04/02 正(@東京)]
最新記事
カレンダー
| 07 | 2025/08 | 09 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
最新トラックバック
アクセス解析
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
みなさん、お久しぶりですっっ
菜です。
ほんとうに
ご無沙汰しています…
もしかして、
「更新しなくなっちゃたんだな~」
と見放されたんじゃないかと、どきどきしておりますが(汗)
今後は、インターンシップ特集号など、
先取りを書いていくぞ!
と、妙さんが決意しています。
本紙、5月20日号にて…
編集員が書いていましたが…
「やっぱ、言葉だけじゃダメだよ。やんないと。」
ということで
早速、編集員で、モニタになってみました。
ちなみにマイボトルはこんな感じ~

自分の好きな写真とか布とかを
入れられます。
けっこうはまります。
すでにモニタになる期間は終了しちゃいましたが、
実は、ずっとタンブラーがほしかった菜は
コッソリ嬉しいです。
ちなみに右は
妙さんのやつです。
左は
塊さんのです。
菜です。
ほんとうに
ご無沙汰しています…
もしかして、
「更新しなくなっちゃたんだな~」
と見放されたんじゃないかと、どきどきしておりますが(汗)
今後は、インターンシップ特集号など、
先取りを書いていくぞ!
と、妙さんが決意しています。
さ
て
・
・
・
( ´▽`)
て
・
・
・
( ´▽`)
本紙、5月20日号にて…
てなカッコイイことを「京都議定書の発祥地に位置する本学は、これまでにも率先して環境保全活動を行ってきた。環境税導入は日本初の試みであったし、有料化せず原則廃止とすることで、レジ袋の削減に成功したのも画期的なことである。
本学は二〇〇二年に環境憲章を制定しており、そこには「大学活動のすべてにおいて環境に配慮し」とある。本学の構成員として、一人一人の主体的努力が重要だろう。小さなことかもしれないが、まずは最初の一歩。マイボトルから始めてみてはいかがだろうか。」
編集員が書いていましたが…
「やっぱ、言葉だけじゃダメだよ。やんないと。」
ということで
早速、編集員で、モニタになってみました。
ちなみにマイボトルはこんな感じ~
自分の好きな写真とか布とかを
入れられます。
けっこうはまります。
すでにモニタになる期間は終了しちゃいましたが、
実は、ずっとタンブラーがほしかった菜は
コッソリ嬉しいです。
ちなみに右は
妙さんのやつです。
左は
塊さんのです。
皆さ~~ん!
お久しぶりでございます。
お元気でしたか?!
なかなか顔をお見せせず、申し訳ございません…。
この一個前の記事が、2月26日だから、
今、4月2日だから…
新年度、スタートですね。(いきなり。)
京大学生新聞も、
(ちょっと、ブログ更新してなかったけど… )
)
今年度は、メンバーも新しく、頑張ります!
本日は、久しぶりに、京都大学に行きました
そして、やはり久しぶりに、いろんな方々にお会いしました
大学の先生でもなく、学生でもない人と言えば、
職員さん!
人間・環境学研究科長の堀先生は、以前
「この三者が協力することが大切だね~」
と仰っていました…。
どちらかというと、背後で大学をバックアップして、
時にヘマをした(汗)学生を励ましてくださる存在が職員さんです…
(↑つまりヘマをしたってことです。)
今日は、そういう影の支えにホンマに感謝した菜でした。
実は、この春、卒業した先輩 を
を
・
・
・
菜が 描*い*てみました!
はい、ど~ん!
これ。
知る人ぞ知る、亜さん!
気になる人は
3月20日号の編集後記を
要チェック!!
あっ、
本年度もよろしくお願いいたします
m(_ _)m
お久しぶりでございます。
お元気でしたか?!
なかなか顔をお見せせず、申し訳ございません…。
この一個前の記事が、2月26日だから、
今、4月2日だから…
・
・
・
・
・
新年度、スタートですね。(いきなり。)
京大学生新聞も、
(ちょっと、ブログ更新してなかったけど…
 )
)今年度は、メンバーも新しく、頑張ります!
本日は、久しぶりに、京都大学に行きました

そして、やはり久しぶりに、いろんな方々にお会いしました
大学の先生でもなく、学生でもない人と言えば、
職員さん!
人間・環境学研究科長の堀先生は、以前
「この三者が協力することが大切だね~」
と仰っていました…。
どちらかというと、背後で大学をバックアップして、
時にヘマをした(汗)学生を励ましてくださる存在が職員さんです…

(↑つまりヘマをしたってことです。)
今日は、そういう影の支えにホンマに感謝した菜でした。
●○●さてさて~●○●
実は、この春、卒業した先輩
 を
を
・
・
・
菜が 描*い*てみました!
はい、ど~ん!
知る人ぞ知る、亜さん!
気になる人は
3月20日号の編集後記を
要チェック!!
あっ、
本年度もよろしくお願いいたします
m(_ _)m

みなさま・・・・・・
今日もご閲覧、感謝いたします。(*^u^*)
・
・
・
覚えておられやすか。 (←えっ誰?)
ーーそう

「さかのぼること、去年暮れ。
本紙 12月20日号、
2面 全学ニュースのトップ記事。」
↑【注】リズムよく。七五調を意識する(←こまかい。)
総長と記者クラブとの定例懇談会、第一回が
催されたので~~ありやしたぁ!!
何と、本日、30日……
「第二回 総長と記者クラブとの定例懇談会」
の開催だ!
皆様、今回特別に、
写真でこいつの
取材裏、
ご紹介を~致しやしょう!
どんなふうに記者懇談会が行われているかというと…
こんな感じ!

場所:今回は本部棟1階の総務部広報課
(前回は本部棟5階の特別会議室)
広報課の職員さんが、
自分たちのデスクを端に詰めて、スペースをつくって下さっていました
(ちなみに今日も広報課の方々が、受付はもちろん
カメラや、配付資料・机やいすの準備などなど…
環境を作ってくださっていました)
はっきり言って前回の方が広くて、机が大きくて、
いかにも会議室やな~という所なのですが、
個人的には、今回のようにアットホームな感じが
とても良かったですね。
松本総長も、
「前とはえらく違うところだね。
でも、今回のような雰囲気もいいね」
と一言添えておられました
まずは。第一幕
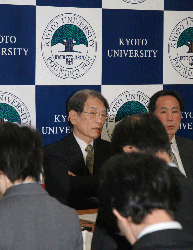
平成21年度の展望を語る
松本総長。
「京大広報」の
2009年1月に出された
No.641号、
に総長の、
本学に関する
課題解決の施策が
載っています
興味深いお話が多かったです
京大に限らず、「大学という場」についてのお話で、
だいたいまとめますと……
短い時間なのに、濃く語られる方だな~と
いつも思うのですが…、
(人の3倍働く総長だと、
ゼミの先生からよく聞きます。
そういえば、この懇談会の前に
環境報告書発行記念シンポにも
出席されていました)
他にも、
「日本は明治初期に、なぜ植民地化されなかったのかご存じですか。
ま、あなたたち(記者)は(それが仕事なんだから)知ってるはずだね」
というお話もありました。
一つの理由として、日本国民の真面目さをあげておられました
争いを避け、自分を主張する以上に和を重んじ、尊ぶ
精神が教育されていたということです。
あるいは、簡単に学校の歴史を振り返っておられました。
「よく外国から来た学者がびっくりしよんねや」
ということで紹介されたのが、
OECDの中で
日本が高等教育にかけるGDPの割合が
最下位(0.5%)であることを危惧されておられました
OECD全体としては3%だそうです。
0.5%と言っても、実際の額としては大きいのですが、
「いっぺん、実際はどうなんか調べてみてほしい。」と
記者に語りかけておられました。
高等教育に力を入れてほしいとのこと。
まだまだ、出てきますが、
これからのブログの中で、ちょくちょく書いていきたいと思います。
やっぱり、どんな組織でも、トップの意識していることは重要ですよね。
さて、ここからは
第二幕・・・
前回の記者懇談会では、医学部・医学研究科を
紹介していました。(もちろん内容はiPS!)
今回はですね、
文学部・文学研究科
です
(総務部広報課のお姉さんに聞いたら、
これから理系と文系が交互らしいです)
①まずは

文学部長・文学研究科長
苧阪(おさか)直行 先生
←パワーポイントを
使っておられます
文学研究科の紹介がありました。
4月から、オーバードクターにリレー講義してもらうプログラムがあるとか!?
易しい専門を1・2回生に導入していくことを考えておられます
苧阪先生は、今回の懇談会に早くから来ておられ、
ご自身から、記者の方に、
「どこの記者さんですか」
という感じで話しかけておられました。
とても優しそうな先生です!
文学部をとても愛しておられるご様子。
菜はカメラマンをしていたのですが、
「東館のところの噴水が良いんだよ 」
」
と
教えてもらいました!
(今もあるのかな??)
②つづいて…

文学部教授の
伊藤邦武 先生
「哲学の教育と研究について」
という題で語ってくださいました
きちんとしたレジュメを作ってきておられました。
苧阪学部長が、伊藤先生を、
2006年には文学部長もされていました。
「自然」と「人工物」についてお話されていたところがあって、
最近は両者の境界がゆらいできているそうです。
動植物の品種改良や、人間における遺伝子治療、
デザイナーズチャイルド、身体に埋め込まれた人工神経装具
などなど…従来の「人間」という概念を考え直さなければいけませんね。
これは哲学の話ですが、
工学部や医学部の学生にも十分関わることや。
会が終わってから、少しお声をかけたら、
「つまらない話で失礼しました」
とおっしゃっていましたが…
そんなことなかったですよ!
研究者の方は、その専門の分野をやっぱり
愛されているはず…
それでも、私たちを気遣って
上のように少し笑って仰っていました…
③次は…

人文科学研究所長
金文京 先生
(右)
漢字情報研究センターが、
教会に似ていることを
話してるところ。
白くてキレイな建物です
人文研は、前身の一つである
「東方文化学院京都研究所」ができて以来
今年で76年になります。
学際的で共同研究・フィールドワークが活発だそうです。
ちなみに、金先生は、
以前「秋の読書特集」に参加してくださいました♪
④最後は…
人文科学研究所准教授
安岡孝一 先生
「松本総長に、
『なんかおもろい話してくれ』
と言われましてね~」
と
「QWERTYの謎」
について話してくれました。
つまり…
問い「パソコンのキーボードは
なぜあんな風に並んでいるのか」
というお題です。
面白いのが、
朝日新聞(東京)2007年5月19日朝刊6頁や、
読売新聞(大阪)2002年5月11日夕刊5頁で、
答え「タイプライターのキー配列を引き継いだ。
活字棒が絡み合わないようにした。
英語で続けて使われる文字は遠くに配列した」
という答えが書いてあるのですが、
全くのガセネタ!
だそうです。

面白そうに聞く松本総長(奥右から二番目)
みんな聞き入っています
ちなみに総長の左は
大西珠枝 副学長兼理事
手前のアップの人は
記者さんです。
早くから来ておられましたね
キー配列にはいろいろ経緯があるみたいですよ
詳しくは安岡先生の著書『キーボード配列QWERTYの謎』
をどうぞ…

…と、ここで
松本先生から安岡先生に質問。
ベルギーかどこかの
タイプライターについて。

総長の質問に安岡先生が
答えます
このあと何度か応酬が続きました!!
なかなか鋭い質問されていましたね。
大学の先生という世界が、
甘くないな~と目の前で見て思いました
でも、同時にアカデミックな雰囲気を体感しました!
ほかの記者さん達もそうだったのでは…!?
今回の記者懇談会では、
松本先生が記者や発表した先生に
話しかける場面が多くて
交流しようとしておられた様子でした。
「京大おもしろいやんか」と思ってもらいたいのでしょう。
前回の時、本紙では懇談会のねらいを
と書いていましたが、総長自身が、これに一致していこうと
されていますね。
ちなみに、一緒に取材に行った「香」は、
「どうして、文学部は、
今機会に
今あまり人気のない日本哲学を
とりあげたのか」
という質問を考えていました。
今回は聞きそびれましたが…
苧阪先生、どうなのでしょうか ??
??
今日もご閲覧、感謝いたします。(*^u^*)
・
・
・
ーーそう


「さかのぼること、去年暮れ。
本紙 12月20日号、
2面 全学ニュースのトップ記事。」
↑【注】リズムよく。七五調を意識する(←こまかい。)
総長と記者クラブとの定例懇談会、第一回が
催されたので~~ありやしたぁ!!
・
・
・
・
・
(で。)
何と、本日、30日……
「第二回 総長と記者クラブとの定例懇談会」
の開催だ!
皆様、今回特別に、
写真でこいつの
取材裏、
ご紹介を~致しやしょう!
どんなふうに記者懇談会が行われているかというと…
こんな感じ!
場所:今回は本部棟1階の総務部広報課
(前回は本部棟5階の特別会議室)
一般紙の記者さん達がずら~っと並んでいます。
広報課の職員さんが、
自分たちのデスクを端に詰めて、スペースをつくって下さっていました
(ちなみに今日も広報課の方々が、受付はもちろん
カメラや、配付資料・机やいすの準備などなど…
環境を作ってくださっていました)
はっきり言って前回の方が広くて、机が大きくて、
いかにも会議室やな~という所なのですが、
個人的には、今回のようにアットホームな感じが
とても良かったですね。
松本総長も、
「前とはえらく違うところだね。
でも、今回のような雰囲気もいいね」
と一言添えておられました
まずは。第一幕
平成21年度の展望を語る
松本総長。
「京大広報」の
2009年1月に出された
No.641号、
に総長の、
本学に関する
課題解決の施策が
載っています
興味深いお話が多かったです
京大に限らず、「大学という場」についてのお話で、
だいたいまとめますと……
と、おおむねこのような感じです。
西洋では、人々は「教会」に献金をしてきました。
それが、中世や近世にかけてです。
現在はどうか。現在は、「大学」に支援をしています。
大学が、精神的支柱として、さらには科学技術の最前線として
教会に変わる役割を演じ始めていると言うことです。
日本国も、そのようになりはじめています。
もちろん日本には元々西洋の教会ほどのものは、ありません。
今まで大学は多くの人材を輩出してきました。
これからは、さらに大学が、「卒業後、帰ってくる場」に
なっていきたい(精神的支柱)。つながりを作っていきたい。
大学が、人を出すだけじゃなくて、
卒業生が大学を頼りにし、いつでも帰ってこれる場所にしたい
大学を人生の基軸にしたい
短い時間なのに、濃く語られる方だな~と
いつも思うのですが…、
(人の3倍働く総長だと、
ゼミの先生からよく聞きます。
そういえば、この懇談会の前に
環境報告書発行記念シンポにも
出席されていました)
他にも、
「日本は明治初期に、なぜ植民地化されなかったのかご存じですか。
ま、あなたたち(記者)は(それが仕事なんだから)知ってるはずだね」
というお話もありました。
一つの理由として、日本国民の真面目さをあげておられました
争いを避け、自分を主張する以上に和を重んじ、尊ぶ
精神が教育されていたということです。
あるいは、簡単に学校の歴史を振り返っておられました。
そして、天武天皇期に学校が創始され、
平安時代には、「大学」
室町時代の「足利学校」
江戸時代には「私塾や寺子屋」
「よく外国から来た学者がびっくりしよんねや」
ということで紹介されたのが、
OECDの中で
日本が高等教育にかけるGDPの割合が
最下位(0.5%)であることを危惧されておられました
OECD全体としては3%だそうです。
0.5%と言っても、実際の額としては大きいのですが、
「いっぺん、実際はどうなんか調べてみてほしい。」と
記者に語りかけておられました。
高等教育に力を入れてほしいとのこと。
まだまだ、出てきますが、
これからのブログの中で、ちょくちょく書いていきたいと思います。
やっぱり、どんな組織でも、トップの意識していることは重要ですよね。
さて、ここからは
第二幕・・・
前回の記者懇談会では、医学部・医学研究科を
紹介していました。(もちろん内容はiPS!)
今回はですね、
文学部・文学研究科
です
(総務部広報課のお姉さんに聞いたら、
これから理系と文系が交互らしいです)
①まずは
文学部長・文学研究科長
苧阪(おさか)直行 先生
←パワーポイントを
使っておられます
文学研究科の紹介がありました。
4月から、オーバードクターにリレー講義してもらうプログラムがあるとか!?
易しい専門を1・2回生に導入していくことを考えておられます
苧阪先生は、今回の懇談会に早くから来ておられ、
ご自身から、記者の方に、
「どこの記者さんですか」
という感じで話しかけておられました。
とても優しそうな先生です!
文学部をとても愛しておられるご様子。
菜はカメラマンをしていたのですが、
「東館のところの噴水が良いんだよ
 」
」と
教えてもらいました!
(今もあるのかな??)
②つづいて…
文学部教授の
伊藤邦武 先生
「哲学の教育と研究について」
という題で語ってくださいました
きちんとしたレジュメを作ってきておられました。
苧阪学部長が、伊藤先生を、
と紹介。心の哲学、言語哲学から生命の科学、
宇宙論の哲学まで、西洋近代哲学と現代の最先端の哲学を
幅広く研究。
西田哲学を継承する旧哲学史第一講座
つまり…いわゆる純哲の担当
2006年には文学部長もされていました。
「自然」と「人工物」についてお話されていたところがあって、
最近は両者の境界がゆらいできているそうです。
動植物の品種改良や、人間における遺伝子治療、
デザイナーズチャイルド、身体に埋め込まれた人工神経装具
などなど…従来の「人間」という概念を考え直さなければいけませんね。
これは哲学の話ですが、
工学部や医学部の学生にも十分関わることや。
会が終わってから、少しお声をかけたら、
「つまらない話で失礼しました」
とおっしゃっていましたが…
そんなことなかったですよ!

研究者の方は、その専門の分野をやっぱり
愛されているはず…
それでも、私たちを気遣って
上のように少し笑って仰っていました…
③次は…
人文科学研究所長
金文京 先生
(右)
漢字情報研究センターが、
教会に似ていることを
話してるところ。
白くてキレイな建物です
人文研は、前身の一つである
「東方文化学院京都研究所」ができて以来
今年で76年になります。
学際的で共同研究・フィールドワークが活発だそうです。
ちなみに、金先生は、
以前「秋の読書特集」に参加してくださいました♪
④最後は…
人文科学研究所准教授
安岡孝一 先生
「松本総長に、
『なんかおもろい話してくれ』
と言われましてね~」
と
「QWERTYの謎」
について話してくれました。
つまり…
問い「パソコンのキーボードは
なぜあんな風に並んでいるのか」
というお題です。
面白いのが、
朝日新聞(東京)2007年5月19日朝刊6頁や、
読売新聞(大阪)2002年5月11日夕刊5頁で、
答え「タイプライターのキー配列を引き継いだ。
活字棒が絡み合わないようにした。
英語で続けて使われる文字は遠くに配列した」
という答えが書いてあるのですが、
全くのガセネタ!
だそうです。
面白そうに聞く松本総長(奥右から二番目)
みんな聞き入っています
ちなみに総長の左は
大西珠枝 副学長兼理事
手前のアップの人は
記者さんです。
早くから来ておられましたね
キー配列にはいろいろ経緯があるみたいですよ
詳しくは安岡先生の著書『キーボード配列QWERTYの謎』
をどうぞ…
…と、ここで
松本先生から安岡先生に質問。
ベルギーかどこかの
タイプライターについて。
総長の質問に安岡先生が
答えます
このあと何度か応酬が続きました!!
なかなか鋭い質問されていましたね。
大学の先生という世界が、
甘くないな~と目の前で見て思いました

でも、同時にアカデミックな雰囲気を体感しました!
ほかの記者さん達もそうだったのでは…!?
今回の記者懇談会では、
松本先生が記者や発表した先生に
話しかける場面が多くて
交流しようとしておられた様子でした。
「京大おもしろいやんか」と思ってもらいたいのでしょう。
前回の時、本紙では懇談会のねらいを
関西には本学の情報は取り上げられるが、他地域にはあまり情報が
伝わっておらず、「京都大学は何をやっているのか分からない」と言われる
現状がある。マスメディアとの日常的な交流を深めることで、
特に東京地方に本学の情報を発信し、「見せることで魅せる大学」
にしていくこと
と書いていましたが、総長自身が、これに一致していこうと
されていますね。
ちなみに、一緒に取材に行った「香」は、
「どうして、文学部は、
今機会に
今あまり人気のない日本哲学を
とりあげたのか」
という質問を考えていました。
今回は聞きそびれましたが…
苧阪先生、どうなのでしょうか
 ??
??
香と菜は先日……
個人的に……
深ぁ~い お話
を、してきました
( ̄~+ ̄)
(ま、大学生だからサっ)←えらそう。
場所は…
ここで…。
そう。。。
有名な、
その後は
「床で作業をしている編集員」(泣)
のために
おざぶとんを買いに行きました。
買い物好き(BY菜)の香が、一瞬で目をつけたのは……

この子。
とうふシリーズの……
「ただのすずめ」
バージョン。
よくみたら小さい足や羽がついてる
当該の編集員(男)は
「かわいいですねぇ」
といいながら、頭に載せていた
…さらに、作業に励みます!!
=追伸=
編集員にスリッパ買ったのですが
足でかすぎて、入らない事件(?)が。
香は、
「そんなばかな。そんな大きさってあるの」
とショックを隠せない。
個人的に……
深ぁ~い お話
を、してきました
( ̄~+ ̄)
(ま、大学生だからサっ)←えらそう。
場所は…
ここで…。
そう。。。
有名な、
『一乗寺中谷』さんです!(HPはコチラ)

右:本日のパフェ
(菜)
左:ロールケーキのお重
(香)
いずれも830円なり
ヽ( ゜ ▽、゜ )ノ 「パクパク」
「…めっちゃおいしい…」




【評】
香のロールケーキは、むちゃふわっで、
生地が、んまい! もっと食べたい……
菜のたべた本日のパフェは、その日ごとに違うみたいですが、
ケーキ(これが食べたかった)もアイス(抹茶最高やん)
も、お団子などなど…が盛りだくさんで満足でした
【結果】
両者共に、「また、ここで話そう。」ということに
んで。
右:本日のパフェ
(菜)
左:ロールケーキのお重
(香)
いずれも830円なり
ヽ( ゜ ▽、゜ )ノ 「パクパク」
「…めっちゃおいしい…」





【評】
香のロールケーキは、むちゃふわっで、
生地が、んまい! もっと食べたい……
菜のたべた本日のパフェは、その日ごとに違うみたいですが、
ケーキ(これが食べたかった)もアイス(抹茶最高やん)
も、お団子などなど…が盛りだくさんで満足でした
【結果】
両者共に、「また、ここで話そう。」ということに
んで。
その後は
「床で作業をしている編集員」(泣)
のために
おざぶとんを買いに行きました。
買い物好き(BY菜)の香が、一瞬で目をつけたのは……
この子。
とうふシリーズの……
「ただのすずめ」
バージョン。
よくみたら小さい足や羽がついてる
当該の編集員(男)は
「かわいいですねぇ」
といいながら、頭に載せていた
…さらに、作業に励みます!!
=追伸=
編集員にスリッパ買ったのですが
足でかすぎて、入らない事件(?)が。
香は、
「そんなばかな。そんな大きさってあるの」
とショックを隠せない。
こんにちは!
最近寒かったですがお体にお変わりありませんか。
今日はなかなか暖かいです
最近は、
こちら!

角川書店さんの
「万葉集」
「ビギナーズクラシックス」
シリーズより
を、楽しんで読んでおります。
ビギナーズクラシックスのシリーズは
表紙がかわいいですね
ちなみに、1月20日号のコラム
万葉集の歌から書きました。
(右下のリンクから読めます )
)
最近は、NHKでも
BSでやっていた「日めくり万葉集」(HPはコチラ)
が再放送(かな?)されていて
万葉集が注目されていますね!
それにしても
もっとこうしたら…と後で思ってしまうところが
毎回毎回ある……
( -_-)うぅ…
-_-)うぅ…
もっと挑戦したいのに
できなかった「悔しさ」は、
流してしまわないで、
ちゃんと蓄えておいて、
強くなっていきたいと思います!
さて。
お口直し
にここで一首。
大伴家持が、三首続けて読んだうちの二首目。
家持の敏感な聴覚に注目です。
さ て 。
あの~…
この前、帰省していましたら
き、霧(きり)が!

午前6:53なり。
朝早くの霧はうつくしいですね
(「朝霧」は秋の季語らしいですが…)
ちなみに霧(きり)と靄(もや)とは
「気象観測においては視程が1km未満のものを霧といい、
1km以上10km未満のものは靄(もや)と呼んで区別する」のだそうです。
へ~
最近寒かったですがお体にお変わりありませんか。
今日はなかなか暖かいです
最近は、
こちら!
角川書店さんの
「万葉集」
「ビギナーズクラシックス」
シリーズより
を、楽しんで読んでおります。
ビギナーズクラシックスのシリーズは
表紙がかわいいですね
ちなみに、1月20日号のコラム
万葉集の歌から書きました。
(右下のリンクから読めます
 )
)最近は、NHKでも
BSでやっていた「日めくり万葉集」(HPはコチラ)
が再放送(かな?)されていて
万葉集が注目されていますね!
それにしても
もっとこうしたら…と後で思ってしまうところが
毎回毎回ある……
(
 -_-)うぅ…
-_-)うぅ…もっと挑戦したいのに
できなかった「悔しさ」は、
流してしまわないで、
ちゃんと蓄えておいて、
強くなっていきたいと思います!
さて。
お口直し
にここで一首。
大伴家持が、三首続けて読んだうちの二首目。
家持の敏感な聴覚に注目です。
あしひきの 八つ峰の雉 鳴き響む 朝明の霞 見れば悲しも
(あしひきの やつおのきざし なきとよむ あさけのかすみ みればかなしも)
万葉集 4149 大伴家持
「山々の峰に雉の声響く夜明けに、たなびいている霞を見ると、
もの悲しい思いに満たされる」
さ て 。
あの~…
この前、帰省していましたら
き、霧(きり)が!
午前6:53なり。
朝早くの霧はうつくしいですね

(「朝霧」は秋の季語らしいですが…)
ちなみに霧(きり)と靄(もや)とは
「気象観測においては視程が1km未満のものを霧といい、
1km以上10km未満のものは靄(もや)と呼んで区別する」のだそうです。
へ~
新春号、
( ´▽`)
本当にまぢか~!
近日降版!
…で、で、で、
新春号の
京大生アンケート!
を、メンバーでかけずり回って(いいすぎ)
取ってきました~
アンケート内容は、こちら

←これに
釘付けのかたも…!
みなさま、
本当にありがとうございます★
m(_ _)m

今年の年明けの瞬間(0時の瞬間!)
あなたは、
どこで
誰と
何をしていましたか?
という極めて単純な質問!
実際に、京大内で
突撃アンケートをとってみると…
(いや~はじめは緊張しますねぇ )
)
 「オレ、おもんないですよぉ~」
「オレ、おもんないですよぉ~」
(訳:私の正月の過ごし方は平凡で取るに足らないものですよ)
や、
 「寝込んでました……」
「寝込んでました……」
という人も。
かわいそう…。でも、私の周りにも
体調を崩してしまっていた人、多かったです。
中には、
 「もちろん答えますよ~。アンケートお疲れ様です★」
「もちろん答えますよ~。アンケートお疲れ様です★」
といういい人も…★わ~ぃ!
一方、
他大生のふりをして答えて下さらない方もいました
「そんな…。うそつかなくても、普通に断ったらいいのに… 」
」
と、ちょびっと傷つきましたが、
やっぱ、
こっちの不足さゆえ
として、謙虚になるべきですよね。
次回には、
みなさんの心を開かせることができる編集員に
なれますように、頑張ります!(決意)
あと、伯さんもアンケ取り係でしたので、
また、面白いお話聞いて、
掲載いたします!
やっぱ、
外に出て、人に触れると
面白いこと起こりますよね~(しみじみ)
さて。
アンケート結果から割り出される、
典型的な京大生の正月とは!?
新春号を乞うご期待
( ´▽`)
本当にまぢか~!
近日降版!
…で、で、で、
新春号の
京大生アンケート!
を、メンバーでかけずり回って(いいすぎ)
取ってきました~
アンケート内容は、こちら
←これに
釘付けのかたも…!
みなさま、
本当にありがとうございます★
m(_ _)m


今年の年明けの瞬間(0時の瞬間!)
あなたは、
どこで
誰と
何をしていましたか?
という極めて単純な質問!
実際に、京大内で
突撃アンケートをとってみると…
(いや~はじめは緊張しますねぇ
 )
) 「オレ、おもんないですよぉ~」
「オレ、おもんないですよぉ~」(訳:私の正月の過ごし方は平凡で取るに足らないものですよ)
や、
 「寝込んでました……」
「寝込んでました……」という人も。
かわいそう…。でも、私の周りにも
体調を崩してしまっていた人、多かったです。
中には、
 「もちろん答えますよ~。アンケートお疲れ様です★」
「もちろん答えますよ~。アンケートお疲れ様です★」といういい人も…★わ~ぃ!
一方、
他大生のふりをして答えて下さらない方もいました
「そんな…。うそつかなくても、普通に断ったらいいのに…
 」
」と、ちょびっと傷つきましたが、
やっぱ、
こっちの不足さゆえ
として、謙虚になるべきですよね。
次回には、
みなさんの心を開かせることができる編集員に
なれますように、頑張ります!(決意)
あと、伯さんもアンケ取り係でしたので、
また、面白いお話聞いて、
掲載いたします!
やっぱ、
外に出て、人に触れると
面白いこと起こりますよね~(しみじみ)
さて。
アンケート結果から割り出される、
典型的な京大生の正月とは!?
新春号を乞うご期待
みなさま、ご無沙汰しております。
京大学生新聞会、今年も謙虚に頑張っていきたいと思います。

お正月、
個人的に、真言宗のお寺に
父親とお参りに行きました★
玄関すぐに置いてあった
生け花。
鶴が、おめでたいですね!
さて、
本当に
みなさんに
支えられている京大学生新聞です。
新春号は12面で頑張っております!
(新春号のデスクは、伯さん)
毎度おなじみの「年頭所感」や、
「滋賀県知事 嘉田さん
のインタビュー」
さらに、
「各界の専門家に聞く
2009年の動向」、
のしっかりした記事を始め、
「京大生 新年アンケート」など
お楽しみ企画もあります!
今、体を張って、最後の大詰めです
乞うご期待
ここで、
年末に事務所の近くで買った
パンを(ぱん!?)
ご紹介↓

いろんな種類があるんだとか…
パン自体はスカスカしてましたが
見た目は癒し系。
京大学生新聞会、今年も謙虚に頑張っていきたいと思います。
お正月、
個人的に、真言宗のお寺に
父親とお参りに行きました★
玄関すぐに置いてあった
生け花。
鶴が、おめでたいですね!
さて、
本当に
みなさんに
支えられている京大学生新聞です。
新春号は12面で頑張っております!
(新春号のデスクは、伯さん)
毎度おなじみの「年頭所感」や、
「滋賀県知事 嘉田さん
のインタビュー」
さらに、
「各界の専門家に聞く
2009年の動向」、
のしっかりした記事を始め、
「京大生 新年アンケート」など
お楽しみ企画もあります!
今、体を張って、最後の大詰めです
乞うご期待
ここで、
年末に事務所の近くで買った
パンを(ぱん!?)
ご紹介↓
いろんな種類があるんだとか…
パン自体はスカスカしてましたが
見た目は癒し系。
こんにちは
お昼休みに
京都大学軽音楽部ジャズ系の皆さんが
ストリートライブしていました★




かっこよかったです!
みなさんノリノリで
音楽好きなんだなぁ
ってすごく伝わってきました



今度の12月21日には
第62回定期演奏会
を、京都教育文化センターでやるみたいです
★★★ジャズ系HPはコチラから★★★

お昼休みに
京都大学軽音楽部ジャズ系の皆さんが
ストリートライブしていました★



かっこよかったです!
みなさんノリノリで
音楽好きなんだなぁ
ってすごく伝わってきました



今度の12月21日には
第62回定期演奏会
を、京都教育文化センターでやるみたいです
★★★ジャズ系HPはコチラから★★★
次号が迫っております!
そうです…
降版前です……
実際的には
新聞原稿を印刷所に送る
締め切りのことです!
てつや~
てつや~
て・つ・や!
がんばれ~~!
――敵は、他人とちゃう!
――敵は、自分自身や!
(自分の世界に完全に入っている編集員)
妥協するな!
……、と、そこに……!?!?

編集長が
お勧め!
「銀のさら」
のおすし


「ほぅら、
目が冴えたろう?」
と編集長がおっしゃったか、
おっしゃらなかったか…
お寿司の写真を
目がとろんとしている
編集員の前で
ハタハタしていたような……
(ハッ!)
※菜の勘違い40%※
ちなみに、
わたくしは
だいじなだいじな
発表を控えているので、
頑張らねば…と思い、
一緒に完徹しましたよ

(本日、無事発表おわりました!)
そうです…
降版前です……
実際的には
新聞原稿を印刷所に送る
締め切りのことです!
てつや~
てつや~
て・つ・や!
がんばれ~~!
――敵は、他人とちゃう!
――敵は、自分自身や!
(自分の世界に完全に入っている編集員)
妥協するな!
……、と、そこに……!?!?
編集長が
お勧め!
「銀のさら」
のおすし



「ほぅら、
目が冴えたろう?」
と編集長がおっしゃったか、
おっしゃらなかったか…
お寿司の写真を
目がとろんとしている
編集員の前で
ハタハタしていたような……
(ハッ!)
※菜の勘違い40%※
ちなみに、
わたくしは
だいじなだいじな
発表を控えているので、
頑張らねば…と思い、
一緒に完徹しましたよ


(本日、無事発表おわりました!)